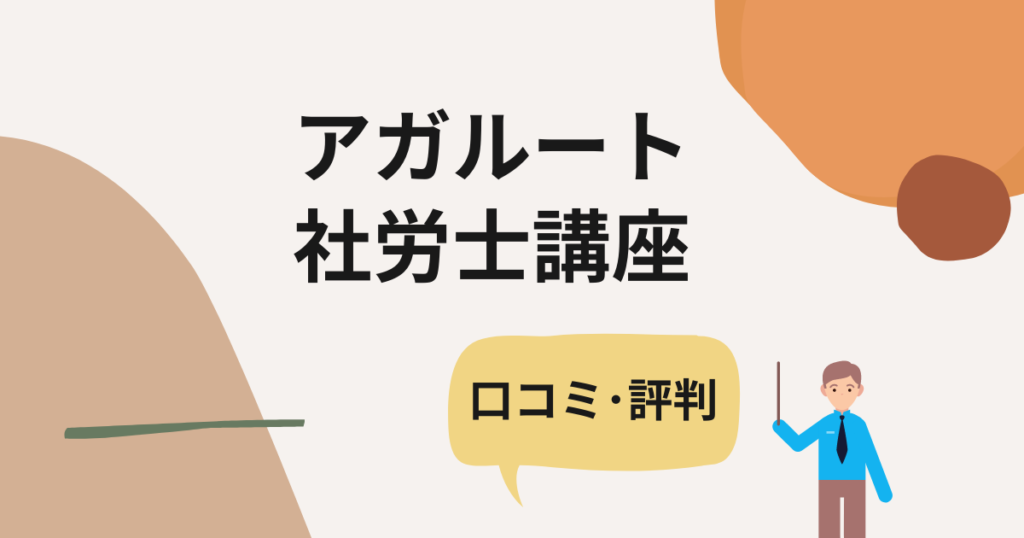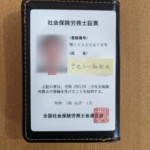労働法判例穴埋め問題③(年次有給休暇・賃金①)|社労士試験の勉強

近年の社労士試験では、判例の出題が増えています。
そこで無料で利用できる「判例の穴埋め問題」を作成しました。
スキマ時間にぜひ活用してください。

穴埋め問題は8つあります。
ブックマーク(お気に入り登録)して活用してください!
利用上の注意点
- 本ページは厚生労働省の「確かめよう労働条件」を複写しています
- 判例の骨子などを穴埋め問題としており、具体的な解説はしていません
- 社労士試験に出題されるのは最高裁判例がメインです。
- 最高裁判例には「★」を記載しています。
- 日本法においては特に最高裁判所が示した判断を「判例」、下級審の判断は「裁判例」と区別されますが、ここではすべて「判例」として扱っています
「年次有給休暇」に関する判例
「年次有給休暇」について、基本的な方向性は以下のとおりです。
【基本的な方向性】
(1) 年次有給休暇の成立要件である(1. 出勤率 )について、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から(2.正当な理由なく)就労を拒まれたために就労することができなかった日は、(3. 出勤日数 )に算入すべきものとして全労働日に含めて算定します。
(2) 年次有給休暇を取得したことにより皆勤手当を減額することなどは、その趣旨、目的、それにより失う(4. 経済的利益 )の程度、年次有給休暇の取得に対する(5.事実上の抑止力)の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇の取得を抑制し、それにより労基法が労働者に年次有給休暇取得の権利を保障した趣旨を(6. 実質的 )に失わせるものでない限り、無効とはいえないとされています。
「年次有給休暇」に関する判例として、以下の事件を紹介します。
★=最高裁判例
- ★八千代交通事件(H25.06.06最一小判)
- ★沼津交通事件(H05.06.25最二小判)
★八千代交通事件(H25.06.06最一小判)
【事案の概要】
(1) 解雇により2年余りにわたり就労を拒まれたY社の社員Xは、解雇無効の判決が確定して職場復帰した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の請求をして就労しなかったところ、Y社は、年次有給休暇の成立要件を満たさないとして、5日分の賃金を支払わなかった。このためXは、年次有給休暇権を有することの確認、控除した賃金・遅延損害金の支払と不法行為による損害賠償を求めて提訴したもの。
(2) 本件では,Xが請求の前年度において年次有給休暇権の成立要件(雇入れの日から6か月の継続勤務期間又はその後の1年ごとにおいて全労働日の8割以上出勤したこと)を満たしているか否かが争われた。さいたま地裁は、使用者の責に帰すべき事由により就業できなかった期間は、「全労働日」に算入し、出勤した日として扱うのが相当として、Xの主張を認容した。東京高裁はY社の控訴を棄却し、最高裁もこれを維持して上告を棄却した。
【判示の骨子】
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から(1.正当な理由なく)就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇の成立要件における(2. 出勤率 )の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして(3. 全労働日 )に含まれるものというべきである。
★沼津交通事件(H05.06.25最二小判)
【事案の概要】
(1) タクシー会社Y社は、労働組合との労働協約において、勤務予定表どおりに勤務した場合には1か月3,100円ないし4,100円の皆勤手当を支給するが、年次有給休暇を取得した場合には皆勤手当の全部又は一部を支給しないこととなった。年休を取得したことによって皆勤手当が減額された運転手Xは、こうした取扱いは労基法に反するなどとして、減額あるいは支給されなかった皆勤手当と遅延損害金の支払いを求めて提訴したもの。
(2) 静岡地裁は、有給休暇を取得した日を欠勤扱いすることは取得を抑制し、公序に反するとしてXの請求を認容したが、静岡高裁は、皆勤手当の減額・不支給が有給休暇の取得を事実上制約する抑制的効果を持っていたとまでは認められないこと等から、直ちに公序良俗に反して無効であるとすることはできないとし、最高裁もこれを支持した。
【判示の骨子】
(1) (現)労基法136条自体は、使用者の(1. 努力義務 )を定めたものであつて、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの(2. 私法上の効果 )を否定するまでの効力を有するものではない。
(2) 年次有給休暇取得による(3. 不利益措置 )は、労基法39条の精神に沿わない面を有することは否定できないが、その趣旨、目的、労働者が失う(4. 経済的利益 )の程度、年次有給休暇の取得に対する(5.事実上の抑止力)の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を(6. 抑制 )し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を(7. 実質的 )に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効となるとすることはできない。
(3) Y社の右措置は、年次有給休暇の取得を一般的に(6. 抑制 )する趣旨に出たものではなく、また、控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどから、年次有給休暇の取得を(7. 事実上抑止 )する力は大きなものではなかったというべきであり、公序に反する無効なものとまではいえない。
「中間収入の控除」に関する判例
「中間収入の控除」について、基本的な方向性は以下のとおりです。
【基本的な方向性】
(1) 使用者の責に帰すべき事由による解雇の場合、労働者は解雇期間中の(1. 賃金支払 )を請求できますが、使用者は(2. 賃金支払 )に当たって、労働者の中間収入分を控除できます。
(2) 控除の限度額については、労基法26との関係から、平均賃金の(3. 4 )割が限度となります。
「中間収入の控除」に関する判例として、以下の事件を紹介します。
★=最高裁判例
- ★米極東空軍山田部隊事件(S37.07.20最二小判)
★米極東空軍山田部隊事件(S37.07.20最二小判)
【事案の概要】
(1) 使用者Yの責に帰すべき事由により解雇された労働者Xが、当該解雇期間中に他の職に就いて利益を得た場合に、Yが賃金を支払う際に、Xは右の利益を償還しなければならないかが争われた事例。
(2) 最高裁は、中間収入は控除すべきだが、その限度は、平均賃金の4割に留めるべきとした。
【判示の骨子】
(1) 使用者の責に帰すべき事由によって解雇された者が解雇期間内に他の職に就いて(1. 利益 )を得たときは、その(1. 利益 )が副業的なものであって解雇がなくても当然取得しうる等特段の事情がない限り、民法536条2項但書に基づき、使用者に償還すべき。
(2) 労基法26条の規定は、民法536条2項の「使用者ノ責ニ帰スヘキ事由」によって解雇された場合にも適用される。
(3) 解雇期間中の賃金全額の請求権を有すると同時に解雇期間中に得た利益を償還すべき義務を負っている場合に、特約がない限り、平均賃金の(2. 4 )割までは控除できる。
社労士にも簿記の知識は必須。
手軽に学ぶなら、すべて無料のCPAラーニングがおすすめ。
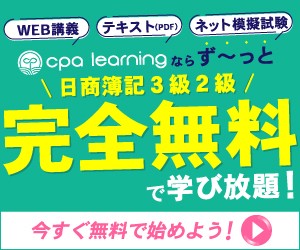
講義動画・テキスト・模擬試験がすべて無料!
多くの人に利用され、すでに45万人以上が登録しています。
個人情報不要で登録できるので、今のうちに登録しておきましょう。
\登録はメールアドレスだけ!/
「割増賃金不払い」に関する判例
「割増賃金不払い」について、基本的な方向性は以下のとおりです。
【基本的な方向性】
(1) 割増賃金請求の場合、要件事実の(1. 立証責任 )は労働者側にありますが、労働者側の証拠が不十分でも、使用者が労働者の労働時間を(2. 適正に把握 )する責務を果たしていないことが考慮され、タイムカード等の明確な証拠がない場合であっても、労働者が作成して使用者に提出する書面(出勤簿、業務日誌等)や個人的な(3. 日誌、手帳 )等によって、一応の立証がされたものとし、使用者側が(4. 有効かつ適切 )な反証をしなければ、労働者の請求が認容されることがあります。
(2) 時間外労働手当に代えて一定額を支払うという(5. 定額残業制 )は、労働基準法所定の計算方法による額以上の金額を支払っていれば、同法37条に違反しませんが、同法所定の計算方法によらない場合は、割増賃金として法所定の額が支払われていることを明確にするために、割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを(6. 明確に区別 )することを要します。法定休日労働の割増賃金相当分、深夜労働の割増賃金相当分についても同じです。また、(5. 定額残業制 )によってまかなわれる残業時間数等を超えて残業等が行われた場合には、その(7. 差額 )を別途支払う必要があります。
「割増賃金不払い」に関する判例として、以下の事件を紹介します。
★=最高裁判例
- ★小里機材事件 (S62.01.30東京地判 S63.7.14最一小判)
- ★高知県観光事件 (H06.06.13最二小判)
- 京都銀行事件(H13.06.28大阪高判)
- ★テックジャパン事件 (H24.03.08最一小判)
- ★医療法人康心会事件(H29.07.07最二小判)
- ★日本ケミカル事件(H30.7.19最一小判)
★小里機材事件 (S62.01.30東京地判 S63.7.14最一小判)
【事案の概要】
(1) Y社は、従業員Xについて、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に加算して同人の基本給とするとの合意がされていることを理由にして、午後7時を超えて勤務した場合のみ、割増賃金を支払ったところ、Xは、午後5時から7時までの時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めて提訴したもの。
(2) 東京地裁の判断は、判示の骨子のとおりであり、東京高裁判決でも是認され、最高裁でも正当として是認することができるとされた。
【判示の骨子】
(1) 割増賃金の計算にあたり、仮に、月15時間の時間外労働に対する割増賃金が(1. 基本給 )に含まれるという合意がなされたとしても、基本給のうち時間外労働手当に当たる部分を(2. 明確に区別 )して合意し、かつ、労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことを(3. 合意 )した場合にのみ、その予定時間外労働手当(固定残業手当)分を当該月の時間外労働手当の全部又は一部とすることができる。
(2) Xの基本給が上昇する都度予定割増賃金分が明確に区分されて(3. 合意 )がされた旨の主張立証も、労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが(3. 合意 )されていた旨の主張立証もない本件においては、Y社の主張は採用できない。
よって、Xの時間外労働に対する割増賃金は、(1. 基本給 )の全額及び各手当の額を計算の基礎として時間外労働の全時間数に対して支払わなければならない。
★高知県観光事件 (H06.06.13最二小判)
【事案の概要】
(1) Y社でタクシー乗務員として勤務してきたXらは、隔日勤務で、勤務時間が午前8時から翌日午前2時(そのうち2時間は休憩時間)である一方、賃金は完全歩合給のみであったことから、Y社に対し、午前2時以降の時間外労働及び午後10時から午前5時までの深夜労働の割増賃金等の支払いを求め提訴したもの。
(2) 最高裁は、Xらの時間外及び深夜の労働の割増賃金を支払う義務があるとした。
【判示の骨子】
本件請求期間にXらに支給された歩合給の額が、Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合においても(1. 増額 )されるものではなく、(2.通常の労働時間)の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを(3. 判別 )することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して労基法37条の規定する時間外及び深夜の(4. 割増賃金 )が支払われたとすることは困難であり、本件請求期間におけるXらの時間外及び深夜の労働について、法令の規定に従って計算した額の(4. 割増賃金 )を支払う義務がある。
京都銀行事件(H13.06.28大阪高判)
【事案の概要】
(1) Y銀行の元従業員Xが、始業時刻前の準備作業、朝礼、融得会議、昼の休憩時間、終業後の残業等について、時間外勤務手当の未払分等の支払を求めて提訴したもの。
(2) 京都地裁はいずれの請求も棄却したが、大阪高裁は、昼の休憩時間を除き労働時間性が肯定し、Xの控訴を一部認容した。
【判示の骨子】
(1) ・・・(略)・・・、Y銀行A支店において、午前8時15分から始業時刻までの間の勤務については、Y銀行の(1. 黙示の指示 )による労働時間と評価でき、原則として時間外勤務に該当すると認められる。
(2) Xは、勤務先には午前8時過ぎ頃までに出勤することを常としていたことが認められるから、手帳に記載のあるなしにかかわらず、上記基準に従い、午前8時15分までには出勤して勤務に従事していたと(2. 推認 )するのが相当である。
★テックジャパン事件 (H24.03.08最一小判)
【事案の概要】
(1) 人材派遣会社Yの派遣労働者Xが、基本給を月額41万円とし、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間について1時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において、法定の労働時間を超える時間外労働については、月間総労働時間が180時間を超えなくても時間外手当を支払うべきとして、その支払いを求めて提訴したもの。
(2) 東京高裁は、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する手当の請求権をその自由意思により放棄したものとみることができる、として180時間を超えない月の請求について棄却した。最高裁第一小法廷は、基本給の一部が時間外労働に対する賃金である旨の合意がされたものということはできず、月間180時間以内の月の時間外労働に対する時間外手当の請求権を放棄したとはいえないことから、割増賃金を支払う義務を負うとして、具体額と付加金について改めて審理するよう高裁に差し戻した。
【判示の骨子】
(1) ・・・(略)・・・
また、上記約定においては、月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と(1. 区別 )されて時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、上記の割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変動し得るものである。そうすると、月額41万円の基本給について、(2. 通常の労働時間 )の賃金に当たる部分と時間外の割増賃金に当たる部分とを(3. 判別 )することはできないものというべきである。
(2) ・・・(略)・・・
★医療法人康心会事件(H29.07.07最二小判)
【事案の概要】
(1) 医療法人Yを6か月で解雇された医師Xが、解雇の無効確認と時間外・深夜労働に対する割増賃金の支払を求めたもの。解雇については最高裁まで一貫して有効と判断されたが、割増賃金については、見解が分かれた。
(2) Xは、年俸1,700万円で雇用され、内訳は、月額賃金が120万1,000円(本給86万円、諸手当合計34万1,000円)、・・・(略)・・・
このように、この雇用契約では、時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金は、年俸1,700万円に含まれることが合意されているが、他方、この年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金にあたる部分が明らかにされてはいなかった。
(3) 最高裁は、年俸制でその年俸のなかに時間外等の割増賃金が含まれるとの合意が有効に成立しているとした東京高裁判決を破棄して、原審に差し戻した。
【判示の骨子】
(1) ・・・(略)・・・労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを(1. 判別 )することができることが必要であり,上記割増賃金に当たる部分の金額が法に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその(2. 差額 )を労働者に支払う義務を負うというべきである。
(2) XとYとの間においては,・・・(略)・・・、このうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかった。
そうすると,本件合意によっては、X に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできないのであり、Xに支払われた年俸について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを(1. 判別 )することはできない。
(3) したがって,Y のX に対する年俸の支払により、X の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。
★日本ケミカル事件(H30.7.19最一小判)
【事案の概要】
(1) 保険調剤薬局を営むY社に勤務していた薬剤師Xが、Y社が固定残業代として支払っている業務手当は、みなし時間外手当の要件を満たさないから無効であるなどとして、時間外労働等に対する未払い賃金等の支払いを求めて提訴したもの。
(2) ・・・(略)・・・
(3) ・・・(略)・・・、本件では、①業務手当が何時間分の時間外手当に当たるのかがXに伝えられていないこと、②業務手当を上回る時間外手当が発生しているか否かをXが認識することができないことから、業務手当の支払を法定の時間外手当の支払とみなすことはできないとして、Xの請求を認容した。このため、Y社が上告したものである。最高裁は、原審の判断は是認できないとして、Y社敗訴部分を破棄し、差戻しを命じた。
【判示の骨子】
(1) ・・・(略)・・・
(2) ・・・(略)・・・
(3) ①本件雇用契約書及び採用条件確認書並びに賃金規程において,業務手当が(1. 時間外労働 )に対する対価として支払われる旨が記載されていたこと、X以外の各従業員との間で作成された確認書にも同様の記載がされていたことから,Y社の賃金体系においては,業務手当が(1. 時間外労働 )等に対する対価として支払われるものと位置付けられていたということができること、
②業務手当(約28時間分の(1. 時間外労働 )に対する割増賃金相当)は,実際の(1. 時間外労働 )等の状況と大きく (2. かい離 )するものではないことから,Xに支払われた業務手当は,(1. 時間外労働 )等に対する対価として支払われるものとされていたと認められる。
その他の判例穴埋め問題
※本ページは厚生労働省の「確かめよう労働条件」を元に作成されております。
関連記事
通信講座を探している方はこちらをご覧ください。
-300x158.png)
独学用のテキストを探している方はこちらをご覧ください。

合格までの勉強スケジュールを知りたい方はこちらをご覧ください。
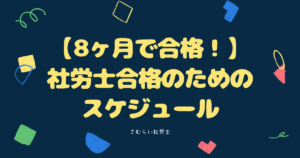
社労士に合格したらこちら。
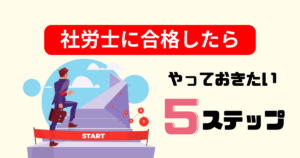
社労士資格を活かして人事で働きたいならこちら。



-1024x538.png)